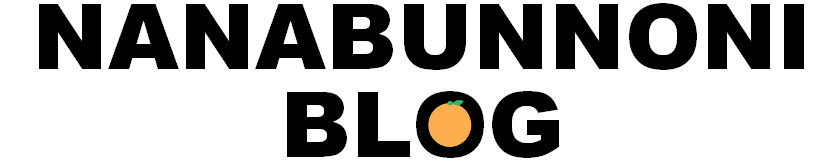最終更新日:2023年5月31日
ルアーフィッシングをしている人にはちょっと厄介な存在、ハクレン。
霞ヶ浦水系を中心に生息している魚ですが、現在では結構様々な水域に見られ、関東在住の釣り人からすると、お馴染みの淡水魚かと思います。(関東平野を流れる大河、利根川は多くの水域に繋がっていますから、それを通じて広がってしまうのでしょう…)
ところで、利根川中流域やその支流等で釣りをされている皆様、春を過ぎる頃になるとハクレンが増える印象はありませんか?
酷いときにはスレ掛りしやすいシャッドやバイブなんかは全く投げられない状況だったり…
今回はあまり知らない人もいるかも?ということで、ハクレンの生態についてご紹介します。
そもそもハクレンとは?
コイ科ハクレン属の魚で、中国四大家魚の一種です。
戦時中に貴重なタンパク源として、食用として国が中国から移植しました。
『中国四大家魚』というのは、アオウオ、ソウギョ、コクレン、ハクレンのことを指します。
ハクレン以外の三種も、同様の理由で移植されたものです。
『家魚』というのは養魚のこと。
これら4種が養魚として重宝されてきたのは、簡単に言えば、この4種を池に飼い、刈った草さえ入れておけば、食物連鎖が成り立つため、飼育がとても容易であるためです。
なお、よく『レンギョ』という呼び名を使う方もいますが、これはハクレン属の総称で、特定の魚を指すものではありません。
バス釣り界ではバイオマニュピュレーションのために雄蛇ヶ池に放流されたソウギョ(草魚)、霞ヶ浦水系や荒川や利根川の温排水で大量に見られるハクレン(白蓮)がよく知られているかと思いますが、アオウオ(青魚)とコクレン(黒蓮)はあまり知られてないかもしれませんね…
オジャガ池の蓮がソウギョによって食い尽くされ、今も皿池状態になっていることは有名な話でしょう。
アオウオは江戸川で過去にメーター級が釣られたことがあり、都市部で出来る怪魚フィッシングとして一部で知られていますね。
コクレンは…よく知りません。爆
※コクレンはそもそも国内に存在する個体数がかなり少ないのか、情報があまりありませんね。
霞ヶ浦をあとにするハクレン、その行き先は?
ハクレンに焦点を当てます。
最も多くの個体が生息しているのは、やはり霞ヶ浦と考えられます。
しかし春先になると、ハクレンの成魚は霞ヶ浦をあとにし、利根川に向かい、遡上を始めます。これが大体4月〜6月くらいです。
遡上して目指す先は、埼玉県は久喜市(旧栗橋町)近辺。
理由は産卵行動を行うためです。
この辺りは、ハクレンの産卵行動が観察される日本で唯一の場所と言われています。(正確にはここ近辺の支流などでも見られます。また、利根大堰が出来る以前は、もっと上流域でも産卵行動が見られていたそうです。)
利根川を遡上してきたハクレンたちは、この産卵エリアにものすごい数で溜まります。
このとき頻発するのが、いわゆる『ハクレンジャンプ』です。

おおよそ60cmから100cmクラスのハクレンが、おぞましい数でジャンプします。
ジャンプする理由は諸説ありますが、自分は「単純にハクレンが臆病な魚であるため、一匹が何かに驚いてジャンプすると、それに連鎖して集団ジャンプが起こるんだ」と考えています。(ジャンプ自体を産卵行動と混同されて説明される人もいますが、産卵行動と直接的な関わりはないと思われます)
ハクレンが産卵する日
産卵エリアにハクレンが集結したら、いよいよ産卵のタイミングを待つばかりです。
一般的にバスやコイ科の淡水魚が産卵行動を起こすきっかけとして、よく言う『大潮満月』が挙げられますが、ハクレンの産卵行動はそれとは特に関係がありません。
下の写真は実際に産卵行動が見られた日の、利根川権現堂樋管付近の様子です。

どんな条件が揃うと、ハクレンは産卵行動を行うのでしょうか…?
濁流がトリガーになるハクレンの産卵行動
どんな条件が揃うとハクレンは産卵行動を行うのか?
答えは『水位上昇』と『濁度上昇』が生じたときです。
平たく言えば、雨台風が過ぎ去ったあと。
その理由は、利根川の通常水位、流量程度では、産んだ卵が孵化する前に、川底へ沈み、泥をかぶってしまうからです。また、濁った水の中であれば、孵化した稚魚が外敵に捕食されにくいからとも考えられています。

スマホで撮影しているのでわかりにくいとは思いますが、上の写真の赤丸内は、オスとメスが身体を擦り合わせて、産卵行動を行なっている様子です。(これはいわゆるハクレンジャンプとはまた別物)
で、こんな状況のときに網を入れると…

ホラごっそり・・・ちょいグロすみません。笑
この透明なイクラみたいなのがハクレンの卵です。ちなみに生臭さハンパないです。爆
何故ハクレンは利根川で産卵を行うのか
話を少し戻しまして、何故ハクレンはわざわざ利根川を遡上して産卵を行うのか?
それは、利根川であれば海水域までにかなりの距離があり、尚且つ止水域である霞ヶ浦水系が下流域にあるという条件が揃っているから…と考えられます。
日本の川は殆どが距離が短く、急流なため、ハクレンの卵が孵化する前に海水域まで流れ着いてしまいます。
孵化したとしても稚魚が流れ着く止水域がなければ、下流に押し流された結果、塩分濃度の変化によって稚魚は死んでしまいます。
そのため、これを踏まえると、産卵エリアの程なく下流に分岐点がある江戸川(利根川から分岐して東京湾に注ぐ)に流れていく卵に関しては、孵化しないまま汽水域まで流れ着いてしまったり、孵化できても止水域に避難できず、そのまま流されていってしまったり…と、なんとも儚い感じです。(まぁ本音はハクレン増えて欲しくないのですが。汗)

上の写真は橋の上から流れていく瀕死のハクレンを撮影したものです。
ハクレンは産卵行動により、かなり体力を消費するようで、利根川や江戸川の橋の上から観測をしていると、産卵当日は瀕死のハクレンが大量に流れていくのが見られます。
多くの個体はそのまま死んでしまうかと思われますが、一部の個体はまた霞ヶ浦水系などの止水域に流れ着いて生きながらえるのかなと想像します。
産卵が終われば利根川のハクレンの数は減る
埼玉県内の利根川水系で釣りをしていると、特に5月〜6月頃はハクレンの大軍に遭遇することが多々あります。
ボートで釣りする場合にはハクレンジャンプに要注意ですし、おかっぱりからでもスレでかけてしまわないように注意しなければなりません…(ちなみに以前一度、80クラスのハクレンさんが危うくカヤックのコックピットにホールインワンしそうになったことがあります。滝汗)
ただ、これまで書いたように、一発大雨が降って産卵が行われれば、ハクレンの数はぐっと減りますので、その時期だけは我慢という感じですね。汗

おわりに
バスだけでなく、他の水生生物たちにも、季節ごとで様々な動きをします。
視野を広げて自然について色々勉強していくと、水辺で起こる出来事を理解できます。
そうすると、一層水辺に立つことが楽しくなるかもしれません♫
追記:霞ヶ浦水系桜川で発生したハクレン大量死について
2023年5月下旬、霞ヶ浦の流入河川である桜川でハクレンが大量に斃死し、Twitter界隈で大きな話題となりました。
ネットニュースでも多く取り上げされていましたが、斃死した数は数千レベルのようで、死魚の回収にあたっている関係者の方々は本当に苦労されているかと思います…

桜川に例年どの程度ハクレンが遡上しているのかはわかりませんが、今回は田土部堰という堰が河川流量の低下で完全に堰き止め状態になっていたようで、ハクレンが大量集結した結果、酸欠で斃死したことが推測されますね。(SNSでハクレンが斃死する前の動画も観ましたが、遡上してきたハクレンが堰下ですし詰め状態でした…汗)

そもそもハクレン自体の個体数が増えれば増えるほど、こういった事象は起こる確率が高まりますし、もしかしたら今年に限り、湖流や各流入河川の流況から、桜川にハクレンを集結させる要因が何かしらあったのかもしれませんし、そこは推察でしか議論できないところでしょう。
ちなみに一部では農薬による影響論が出ていましたが、上流から農薬が流下してきた場合、小さい魚から先に、片っ端から死んでいきますので、そこの可能性は低いでしょう。
あ、余談ですが、これだけの死魚を出すんなら、数十キロ単位とかの原液農薬を不法投棄しない限り無理ですね。土壌からの流出レベルとかでこんなこと起きません。(きっぱり)
流石に事案の規模がでかいので、自治体の環境センターあたりが主要な毒物検査は当然してるでしょうし、場合によってはQ-TOF/MSとか使って有害物質一式のスクリーニング検査までしてると思いますよ。
というわけで、釣り人ならまずは魚のルーツや生態を抑えておきましょうねってことで、理系釣り人の戯言を終わりにします。
ではでは🙏