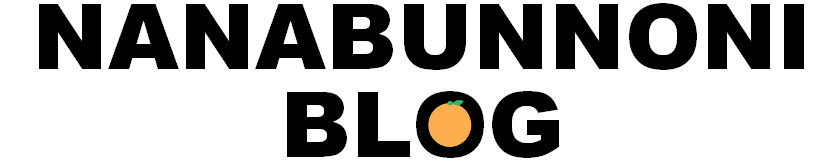ハンドメイドルアーに使われる代表的な木材といえば、やはり「バルサ」だと思います。
しかしこのバルサ、皆さんご存知のとおり加工性が良い反面、しっかりと下処理してあげないと強度的にはルアーとして全く使い物になりません。
今回は「バルサルアーのアンダーコート」について、自分が現在採用している方法をご紹介します。
どうする?バルサの下処理
というわけで今回は自作ルアーをバルサで製作する際に、下処理、いわゆるアンダーコートをどう行うかという話に関してです。
先に言っておきますが、今回ここで紹介する手法が正解・優れているとか、そういう話では全くありませんのでご注意ください。また、素人の戯言ということもご承知おきください。
そもそも、本気のルアービルダーさんは自身のルアーに施している下処理や塗装技術、トップコートの手法なんて絶対に口外しませんから…笑
製作2年目の素人的には、今こんな感じでやってみていますよ〜くらいの内容で読んでください。
自作ルアーの製作を始めた当初、特に深いことは考えず、教科書に載っているような手法を行っていました。
ざっくり言うと、バルサ材をある程度成型したのち、そのまま市販のセルロースセメントでディッピング(ドブ漬け)。
軽いサンディング(ヤスリがけ)とディッピングを数回り返して被膜が大体出来上がったら下処理終了…という感じ。
ただこの手法だと「やたら手間と時間がかかる」というデメリットがありました。(あと、ちゃんとしたセルロースセメントを使わなかったり、正しい処理ができていないと強度が十分に出ない)
そのため、現在は次項で説明する方法に変更しています。
現在のアンダーコート手順
ではここから、具体的に今自分が行っているアンダーコートの方法について説明していきます。
ちなみに、もちろん使う木材によってもアンダーコートの方法は多少変えているので、下記の手順は「割りと硬めのバルサ材でクランクベイトを作るとき」に行っているものになります。
バルサ材と一口に言っても、中身スカスカで柔らかいバルサもあれば、ガチガチに詰まっていて檜みたいに硬いバルサもありますからね…購入時は実物見てよく選定することをオススメします。
1.強制乾燥と加温
まずはバルサボディの成型がある程度整ったところで、粗目のペーパーで軽くヤスリがけしたのち、強制乾燥器に入れてスイッチオンします。

強制乾燥器というのは見てのとおり、段ボールと布団乾燥機で超簡易的に製作した乾燥器です!!(恥)
段ボールにタオルを被せて程よく空気を逃がさないようにして、スイッチオン…内部の温度はおおよそ50~60℃程度になります。
これでバルサ材に含まれている湿気を強制的に飛ばします。(特に夏場はかなり湿気を含んでしまうので、非常に重要な工程です。もちろん冬場もやりますが。)
2.セルロースディッピング
続いてそのままの流れで、出来れば乾燥器の中で加温されたバルサボディを冷めないうちに、用意していたセルロースセメントに漬け込みます。
セルロースセメントは、プロビルダーさんからアマチュアビルダーさんまで幅広く愛用されているFOK(藤倉応用化工株式会社)製のセルロールセメント「HY-100D」です。
FOKセルロースは他社品と比較して、もの凄く濃いセルロースセメントであるため、同社で販売している薄め液(#300ラッカーシンナー)とリターダー(アノン)で希釈しておきましょう。
※希釈率は何となく伏せておきますが、木材に含浸させるためにはある程度薄めるべきですね、はい。
FOKセルロースは、釣具屋さんとかで置いてあるわけではないので知らない方も多いかもしれませんが、ネットでくまなくリサーチすると情報がポツポツ出てきますよ。
購入ルートは基本、藤倉応用化工の本社に出向いて直接購入、またはオンラインショップのみと思われます。
余談ですが、釣具屋で良く見かけるナガ〇マのセルロースセメントはオススメしません。
どうしても釣具屋で売っているものを…という場合にはハンクル製のセルロースセメントにしましょう。(詳細割愛)

最初のディッピング時間の目安は「バルサボディから気泡が大体発生しなくなるまで」という感じで自分は考えています。
10分やら30分やら1時間やら、色々な意見があるでしょうが、とりあえず長く漬け過ぎると折角貼り合わせた接着面が溶剤に侵食されるのでよろしくないと自分は考えています。
1回目のディッピングが完了したら、屋根のあるところで陰干し完全乾燥させます。

乾燥に伴って、バルサが締め付けられて硬くなっていきます。締め付けられることで当然変形を起こすこともあります。
なので、ここまでのサンディングはざっくりで、この工程のあとにしっかり整えていきます。
主に使用するのは3M製のスポンジヤスリです。
スポンジヤスリはアタリがマイルドになるので、クランクベイトのような曲面を整えるにはもってこいのアイテムです。
ある程度整ったところで再度セルロースセメントにディッピングします。
漬ける時間は1回目よりも短めで大丈夫かと思われます。なお、乾燥時は1回目とは逆側から吊るします。
このような作業(軽いサンディングとセルロースディッピング)を数回繰り返します。
木目の凹凸は完全に消え切らなくても良しとしますが、ディッピングと乾燥をした後に、全体的にツルンとした感じになれば十分です。(説明下手ですみません)
3.エポキシアンダーコート
セルロースセメントによる工程が終わったら、再度アタリを付けるためにスポンジヤスリ(スーパーファイン)で軽くサンディングします。
※セルロースセメントに含まれるシンナーが残留してると次のエポキシコートを侵食するので、乾燥には十分な時間をとります。
それと、リップパーツはもうこの時点で完成させて、リップスロットル(リップの差し込み口)もヤスリで整えたりバイスで下穴を空けたりして、あとはもうエポキシ接着剤でリップを装着するだけの状態としておきます。(リップパーツを接着するのは塗装やトップコートを終えたあと)
その後、表面を脱脂した後に、エポキシコーティング剤を筆で薄塗りします。
使用するエポキシは、コニシのボンドEセットがメジャーかと思いますが、ガイドスレッドのコーティングで使用するジャストエース製のエポキシコート剤なんかも使えます。あとはナガシマのエポキシとかも。それぞれ使うコツ(熱をかけて粘度を調整するとか、硬化不良が起きないように配合率を工夫するとか)があるので、その辺は実際にやってみて模索するのが良いと思います。
※雑な説明で申し訳ないなと思いつつ、この辺についてはやっぱり実際に作業してみて経験積むのが一番近道なので…
筆はダイソーで売っているナイロン製の平筆でOKですが、使う前には一度シンナーで洗ってから使用します。
気泡をなるべく噛まずに、薄く、均一に塗るためにドライヤーでの加温はマストですが、熱をかけ過ぎると部分的に硬化反応が促進されて(?)仕上がりにムラが出るので要注意です。
ちなみにエポキシを混合する容器は、アルミ製のものだと熱伝導率が高くて加温しやすいです。(自分は100均で購入。使用後はシンナーで拭き取って繰り返し使っている。なお筆は使い捨て。)
エポキシが均一にコーティングできたら、コーティングマシーンにセットして、硬化が完了するのを待ちます。
ハンドメイドルアーの製作過程で、トップコーティングされたルアーが、機械でくるくると回されている景色を見たことがある方は割と多いかと思います。 今回は以前製作したロッドフィニッシングモーターを活用して、ルアーのコーティング時に使える「3[…]
おおよそ一晩回していれば液ダレで不均一になることはまずありません。(もちろんエポキシの種類や室温にもよりますが)
その後、2~3日間は完全硬化するまで一切触らずに、吊るして放置します。
4.塗装前のサンディング
エポキシが完全に硬化するとこんな感じに仕上がります。
つるつるピカピカパーフェクトッ!!…と言いたいところですが、実際にはよく見ると部分的に少し波打っていたり、気泡が抜けたあとが残っていたりします(^_^;)
ですがあくまで下地ですから、ここはまた再び軽くサンディングして、面を整えればOKです。軽いサンディングで整わないくらい不均一になっていると、しっかりサンディングしたあとで再度エポキシアンダーコートの工程を踏むような感じになります。
5.その後の工程
この後の工程について、ざっと書いておくと…
- サーフェイサー(下地塗装)
- 本塗装、色止め
- 目入れエラ入れ・ドット容れ、色止め
- プライマー
- トップコート
…という感じです。
まだまだ工程が多いように見えますが、アンダーコートが完了したあとの塗装・コーティング工程は楽しいので全然頑張れます👍
リップの切り出しやウエイト仕込み・アンダーコートは地味だし時間かかるし、丁寧にやらないと結局最後に残念な仕上がりになるし、個人的には楽しいとは言い難い辛い作業…ですね、はい。苦笑
まとめ
というわけで今回はここまで。
色んなコーティング剤があると思うのであくまで一例ですが、イメージとしては【染みチョコラスク】です。
ラスク(バルサ)をチョコ(コーティング剤)で硬くするとしたら、まず染みやすい粘度の低いチョコに浸して含浸させて乾燥、その後、粘度と硬度の高いチョコでコーティングしてガチガチに固める、というようなイメージ。(わかりにくい?汗)
いずれ現状やっているハンドメイドルアーの製作方法を全てまとめてみようと思うので、少しずつこういった記事を書き溜めていこうと思ってます。
あとは近々クランクの目を入れる方法とかも書いてみようかな?と(たまに聞かれるので)。
まぁただただ超地道にやってるだけなんですけどね。笑
この投稿をInstagramで見る
1年ちょっと前から少しずつ手を出したハンドメイドルアーですが、気が付けば自宅には様々なハンドメイド用品が揃ってしまいました。汗 そして自分で言うのもアレなのですが、徐々に不満をあまり感じないルアーも製作できるようになってきました。(も[…]