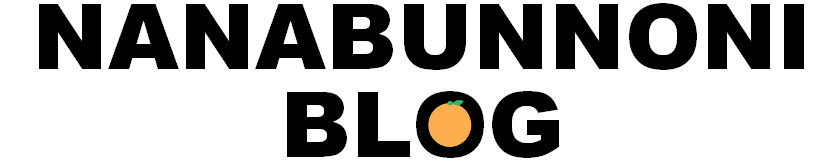リールカスタムにどっぷり浸かってしまった人が行き着く先、「リールペイント」…の前に、とても重要な下処理である「塗装剥がし」。
素人なりに試行錯誤してみたのですが、その結果は…(゜_゜)
リールの塗装を剥がしたい
はい、ということで禁断の(?)リール塗装に手を出したみかん🍊です。
なんでこういうことに手を出してしまったかというと、単刀直入に言えば「01カルカッタコンクエスト50のゴールドを剥がして、シルバーにしたい。」というものでした。

6年ほど前、14カルカッタコンクエスト100/101の登場に伴い、手放してしまった01カルカッタコンクエスト100及び50… しかし先日「01カルカッタコンクエスト50」を買い戻すことを決意! 現在も愛用し続けている人も多い旧カ[…]
カルカッタコンクエスト特有のシャンパンゴールドも素敵なのですが、きらびやかなゴールドカラーはサードパーティが販売するカスタムパーツと組み合わせる際に、色を選んでしまうということは否定できません…(^_^;)
そんなわけで、もうやってしまおうと。
カルコンゴールドを剥がして地のシルバーを剥き出しにしてやろう、と思い立ってしまったわけです。
リール塗装の種類
…と、その前に、まずはリールの塗装に関して整理してみます。
リールの塗装は大きく分けて、以下の3種類が主かと思います。
- プライマー+樹脂塗料を吹き付ける通常の塗装
- メッキ加工処理
- カラーアルマイト処理
例えば強化樹脂に塗装を施す場合には、①の手法が主になっているかと思います。市場のリールにはこれが最も多く見られるヤツですね。
続いて②のメッキ加工、代表的モデルといえば、やはりシマノのアンタレスでしょう。ザ・メッキな鏡面処理加工が施されているのはあまりに有名です。
そして③が今回のターゲットであるアルミ合金ボディであるカルカッタコンクエストなどに採用されている手法。カスタムパーツ屋さんからリリースされているジュラルミン製パーツも、ほとんどがカラーアルマイトによる色付けがなされているかと思います。

リールの塗装どう剥がす?
さて本題ですが、これらのリール塗装をどう剥がすか?
今回の件についてはかなり頭を悩ませたし、ネット情報を探りまくりましたよ…
塗装剥離の基本ではありますが、大別すると化学的アプローチと物理的アプローチの2つに大別されるかと思います。
化学的アプローチについて
化学的にアプローチする方法だと、主だったものはいわゆる「溶剤に漬け込む」という手法かと思います。
ここで言うと溶剤というのは有機溶剤のことで、商品名だと「ラッカーうすめ液」なんかで販売されているやつです。(成分としてはアルコール類やアセトン、トルエンなど)

と言ってもリールに施されている塗装は、往々にして薬品耐性が高いように仕上げられているため、一筋縄ではいかないことも多々あります…(もちろんモノにもよりますが)
それはさておき、メッキやアルマイトなど、金属表面処理に対しては有機溶剤の漬け込みなんかしても当然無意味です。

じゃあどうすれば…
メッキ処理は今回調べていないので不明ですが、アルマイトの場合には表面のアルマイト皮膜を溶かすことでその塗装を剥がす(というか溶かす)ことができます。

上の画像はカスタムバーツ屋さんのカラーアルマイトされたハンドルロックナットを、実験的にアルマイト剥離させたものです。
使ったのはコレ。

はい、排水溝掃除に使う「パイプユニッシュ」とトイレ掃除に使う「サンポール」。
パイプユニッシュに含まれる次亜塩素酸と水酸化ナトリウムがアルミ被膜を溶かし、その後に発生するスマットをサンポールに漬けて溶かす…という手法です。
※2つの薬液は絶対に絶対に混ぜないでください!塩素ガスが発生して最悪天に召されます。
物理的アプローチについて
対して物理的アプローチとなると、もう少し単純な話になります。
要は対象物に何かしらのものをこすりつけることで表面を削る、というだけの話です。
それが紙やすりを人力でこすりつけるのか、グランダーやリューターによるバフ研摩をするのか、サンドブラスト機やバレル研摩機を使うのか…
手法は様々ありますが、「表面を削る」ということに変わりはありません。
バフ研摩とは綿やフェルトで作られた「研磨バフ」に研磨剤を塗り、それを高速回転させて対象物の表面を研磨するというものです。(身近な話だと車のくすんだヘッドライトを磨くとかにもやられる手法)
電動ドリルやハンドリューターをすでに持っていれば、これが一番手頃で楽な手法かと思います。
サンドブラスト機やバレル研摩機については、もはや本業の方が使うです…自宅で素人がどうのこうのっていうものではないので省略します。(これらについても個人客を受注してくれるところとかだいぶ調べましたが…笑)
双方のメリット・デメリット
化学的アプローチと物理的アプローチについて概要や具体例を挙げてみましたが、双方のメリット・デメリットについてまとめると以下のような感じかと思います。
| 化学的アプローチ | 物理的アプローチ | |
| メリット | ・凹凸部分関係なく、対象物の表面全体を塗装剥離することが可能。
・作業時間が短い。 ・薬液さえ正しいものを選定できれば作業者のスキルがなくても成功することが出来る。 |
・研磨したくない部分についてはそのままにすることができる。
・表面の状態を確認しながら慎重に進めることができる。 |
| デメリット | ・知識や経験がないと塗装だけでなくその下の本体にダメージを及ぼす可能性がある。
・危険な薬品を取り扱わなければならない。 ・本来は削りたくないネジ穴等も溶かしてしまう。 |
・作業者の高いスキルがなければ美しい仕上がりは望めない。(特に凹凸部分)
・様々な工具が必要不可欠。 ・作業者によっては作業時間が膨大にかかる。 |
※私は本業の人ではないので、あくまで素人考えで書いたものです。内容に違いがあってもご容赦を…
ポリッシュ加工に挑戦!がしかし…
以上を踏まえまして、私が選んだ手法はコレ。

そう、サンドペーパーと研磨剤を使ってひたすらこする!!(ザ・原始的)
というのも、当初はパイプユニッシュでアルマイト溶解とか考えていたのですが…シマノさん…

なんかこれなんか特殊な表面加工してるでしょ…
上に載せたハンドルロックナットとは全く異なり、ちょっと漬けたくらいじゃびくともしませんでしたよ(^_^;)
もちろん長時間ドブ漬けしていればイケるかもしれませんが、化学的アプローチのデメリットに書いたように、それだとネジ穴やペアリングを収める部分を溶かし過ぎてボディが再生不能になることも往々にしてありえる…
というわけで自分は最も原始的なアプローチで、目に見える部分だけゴールドカラーを削り落としてき上げる…という道を選びました。汗
で、IDAY。

2DAY、3DAY…

4DAY、5DAY…

よし、できたよ!!!!!
と、言いたいところでしたが…
リールのボディというのは小さい上に凹凸もたくさんあり、やすりだけでは届かない部分が多々あります。

そんな場所はハンドリューターを使って研磨剤を付けたバフをこすり当てていくわけですが…まあこれが中々削れないのなんのって。

シマノさん、あんた一体どんな表面加工してんの?(褒めてます)
そんなわけでしてね…
あまりに大変すぎるので、自分、無垢シルバーは諦めることに決定いたしました。(白目)
なんか「そこまでやったなら最後までやれよ」とか言われそうですが…

自分が諦めた一番の理由はココ。
当然なのですが、リールフットって取り外しできませんよね…
まぁカシメをドリルで潰して取り除けば出来なくはないのですが、そこまでしたくはないな…と(^_^;)
自分の技術や工具では、リールフットを外さない限り、その周辺については磨ききれない部分が多く残るのは明らかだったので、諦めることとしました。
ということで、「素人がカラーアルマイト+コーティングが施されたアルミボディをポリッシュ加工で無垢アルミボディ化することは困難を極める!」というのが私の結論です。
もちろん磨きやすい箇所だけなら、素人でも時間さえかければ鏡面加工レベルの仕上げはできるんですけどね…
まとめ
長くなりましたが、リールの塗装(というかアルマイト層を削って落として無垢アルミボディ化)は中々厳しいということがよ~くわかりました。
なんせ研摩に費やした時間はトータルで10時間近く、右手はガチで腱鞘炎になりかけましたからね。爆
研磨技術に無知な方は挑戦しないことをおすすめします♪
…さて、この中途半端な無垢カルコンボディ…当然このままでは終われませんよ。

しっかりと責任を持って仕上げますが、続きはまた別記事で\(^o^)/
Huanyu KT6808 磁気バレル研磨機 ロータリーバレル サビ取り ジュエリー/アクセサリー/金属/パーツ研磨 (小型)