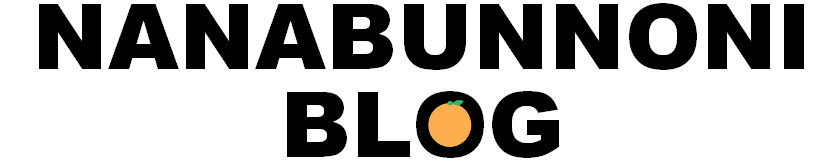使い込まれたコルクグリップは味のあって好き!という方もいるかと思いますが、経年劣化で穴ぼこだらけになるのはコルクグリップの欠点とも言えます…
というわけで今回はコルクグリップの目抜けを修理する方法をまとめます!
コルクグリップを蘇らせよう!
こんにちは、コルクの風合いは昔から好きで、愛竿の多くはコルクグリップなみかん🍊です。
しかし冒頭にも書いた通り、コルクグリップには「経年劣化が激しい」という欠点があります。
まぁEVAグリップでも使い続けていくと表面の細孔がつぶれたり目詰まりしていわゆる「テカリ」が出てしまうという欠点があるので優劣はつけがたいところですが、コルクグリップは使っていくにつれ穴ぼこだらけになり、最悪割れてしまうということもあります…

コルクの目抜け・痩せとは?
釣り歴がある程度ある方は当然ご存知でしょうが、コルクは経年劣化と共に「目抜け」というものが起きます。
新品コルクグリップはこの穴が小さい上に、キチンとパテ埋めされているのでつるんとキレイな状態なわけですが、コルクが痩せてくると穴が大きくなってパテが抜けてきてしまう、という感じかと思います。
※コルクはコルク樫という木材の樹皮なので、吸湿や乾燥を繰り返すうちにこのような状態になってしまうのだと解釈していますが、合ってますかね…(゜-゜)?
コルクの激しい痩せ・割れまでいくともうグリップ交換をするしかありませんが、その前段階であれば、見た的にある程度キレイな状態には戻せるので、今回は目抜けしたコルクの修復方法を紹介します。
コルクグリップの修復方法
というわけで4ステップでコルクグリップの修理をやっていきます。
ここに書く方法はあくまで自分のやり方なので、100%正しい方法とは限りません。
決まりの文句になりますが、DIYはあくまで自己責任でお願いします。
1.汚れを落とす
まずは酷使したコルクグリップ表面にこびりついた汚れを落としていきます。
中性洗剤くらいなら大丈夫かと思いますが、対象が天然素材ゆえにちょっと気持ち悪いので、メラニンスポンジや鍋のコゲ落とし(アクリルたわし的なもの)でぬるま湯をぶっかけながらガシガシこすります。
はい、ざっくり汚れが落ちました。(ここでの汚れ落としはざっくりです)
汚れが落ちてコルク自体はキレイになっていますが、それゆえに逆に目抜け部分が目立った感じになりましたね。
水を含んだ状態で次工程に進むと色々不具合あるので、最低一晩は乾燥させておきましょう。
2.マスキングをする
次にマスキングです。
これは工程3のあとでもいいと言えばいいものですが、今回は先にマスキングをしておきました。
マスキングに使用するのは普通のマスキングテープでもいいですし、正直ビニールテープとかでもいいと思います。(湾曲した面にピッチリ貼れるのでむしろビニール系のテープはイイ。でもモノによってはのり残りしてベタベタする場合があるので注意)
とにかく他のロッドパーツ部分を守れれば良いので、ざっくりなマスキングでもOKです。
3.ウッドパテで目抜けを穴埋めする
ではいよいよ目抜けの穴埋めを行います。
ここで登場するのが専用コルクパテ…ではなく、こちらのパテです。(ででん)
接着剤界隈ではお馴染みの【コニシ】のウッドパテです。
もちろん専用パテでもいいのですが、今回はホムセンなどで誰でもどこでも気軽に入手できるコチラを使っていきます。
但しこれ、決してウッドパテなら何でもイイというわけではないので十分注意してください。(理由は後述しています)
こんな感じでウッドパテを少量出しつつ、小さなヘラや指などでコルクの目抜け部分に押し込んでいきます。
目抜け箇所が多いと、地味に時間のかかる作業です。汗
また大きな穴の部分ほど乾燥後の肉痩せが起きるので、少しだけ盛るくらいの気持ちで塗布します。
盛り過ぎたり不均一になってしまった箇所については、乾く前であれば湿らせた布などでなでると表面を上手く均せます。
ただしやり過ぎると折角盛ったパテがどんどん薄くなってしまので、その辺は状態を見つつトライしてみてください。
パテ埋めが完了したら乾燥させます。
商品説明には「切削・塗装などは24時間以上経過してから」とありますので、それに従って乾燥時間をとるようにします。
4.サンディングで仕上げる
最後はサンディング(やすりがけ)です。
ダイソーで耐水サンドペーパーセットを買ってきました。(というかコレいつも家にたくさんストックあるのですが。笑)
いろいろな番手のものがセットになっていて非常に便利なのです♪
#240でザックリ整えたあと、#400で仕上げていく感じです。(削りすぎると当然コルクグリップそのものがどんどん削られてしまうので、加減をしながら作業しましょう)
最後に表面の削り粉を乾拭きで仕上げて終了です!
うん、いい感じではないでしょうか…?個人的には満足な仕上がりですぞ!!
注意その1:ダイソーウッドパテはオススメしません
今回の作業に関してまず一番に注意しないといけないのは「パテの種類」です。
実は「コルクグリップ 目抜け 修理」とかでググると一番上に出てくるサイトさんの真似で、当初はダイソーで売られている100均ウッドパテを使おうと計画していたのです。
…が、これはNGでした。理由は下の通りよ…
まず木片にコニシのウッドパテとダイソーウッドパテ、両方を塗りました。そして24時間放置し完全乾燥。
そして実験。
この木片を1分間水に浸してみます。すると…
この投稿をInstagramで見る
そう、このウッドパテ、乾燥しても水に少しでもつけておくとドロドロに溶けてきます。
つまりこれを塗ったグリップを雨の中で使おうもんなら…です。
一口にウッドパテと言っても、エポキシ系やらアクリル系やら水性やら色々あるので、気を付けなくてはなりません。
まぁどうしても失敗したくないなら専用コルクパテを使っておいた方が間違いない…かも?
でもコニシのウッドパテは自分が実験済みなので、大丈夫かとは思いますけどね…(^^)
注意その2:コルクと色が合わないことは多々ある
もう1つ注意なのは、パテの色と塗布するコルクの色が合わないというのは多々あるということです。
特にジャストエースさんのコルクパテ「CS-01」は色が結構薄く、白っぽいので目抜けを埋めた部分が逆に目立つということも…(^_^;)
※上画像はジャストエース公式ブログより引用。塗布・乾燥後、時間と共に多少は色が馴染んでくるようですが、ユーザー口コミだと「ちょっと白すぎる」という意見が目立ちます。
これを改善するために、アクリルカラーの黒や赤、黄色をパテに混ぜ込んで調色するという方法もあるようですが、自分はそこまでやっていません。
セメダインのウッドパテ(ウラン)はそこまで白っぽくなく、ある程度なじむし、まぁそこまでしっかり合わせなくてもいいや…という程度で考えているので。笑
まぁそういうやり方もあるみたい!ということだけご紹介しておきます!
まとめ
というわけでコルクグリップの補修方法についてのまとめでした。
もちろんこんなものは釣果には関係ないと言えばそうなのですが、キレイに整えられたタックルを使うのは気持ちいいものです。
冬の間にタックルのメンテナンスをしておくのも良いかもしれませんね♪
最後に今回使用したものをまとめて終了とします(^^)/
【今回の作業で使ったもの】
- コニシ ウッドパテ
- 耐水ペーパーサンドセット(#240~#400)
- メラニンスポンジ
- 捨ててもいいボロ布
ここ数年?ロッドのグリップに熱収縮ラバーチューブやグリップテープを巻く方が結構増えた気がします。 自分もグリップに何かしら巻いておくことが多いのですが、今回はそれらのメリットやデメリットを考えます。 グリップテープを巻くメリット […]
今後はオカッパリをもう少し頑張りたいなぁ…と思っていたところ、オカッパリ用のロッドホルダー・ロングランディグネット・メジャー(スケール)等々…道具が色々欠如していることに気が付いてしまいました。汗 そこで今回は板メジャースケール(また[…]