2019年9月上旬に関東を直撃し、甚大な被害をもたらした台風15号…
通過後にニュースとなった霞ヶ浦水系におけるハクレン等の大量死について、釣り人界隈では「稲渋(いなしぶ・わらしぶ)が原因だ!」と騒がれていました…
が…あの、稲渋って自分初めて聞いたんですが、一体なにそれ…?汗
ということで、理系の人的に色々と疑問に感じることがあったので、自分なりに「稲渋」について調べてみました!
台風15号通過後、ハクレン等が大量死
メディアでも取り上げられていたのでご存知の方もいるかと思いますが、台風15号が関東を通過したのちの9月10日午後、新利根川や破竹川でハクレンを中心とした大型魚が大量死するという現象が起こりました。
【茨城新聞】ハクレン大量死は酸欠の可能性高く 新利根・破竹川、県回収へ
報道では「県水産試験場内水面支場で調べた結果、酸欠による死亡が濃厚と判明した」とのことでしたが、釣り人界隈では死因について、「稲渋」というワードが飛び交っていました。
実は「稲渋」というワード、自分は今回のこのニュースが話題となって初めて知ったワードでした…
仕事上、水に関することはそこそこ知識があるのですが、「稲渋?そんなの聞いたことないんですが…え?しかも魚を死に追いやるほどの物質って…大丈夫それ?汗」となったんです(^_^;)
そこで「稲渋」についてググってみると、出てくるのはほぼ全て釣り関連のブログやサイトで、学術的なものは何も引っかからない…
ただ、台風15号が通過したあと、川がいつもと違った赤茶色?のような凄い濁り色になったという目撃情報はSNSや釣りブログで見かけるので、何かしらの原因はあったのだろうと思い、気になって色々調べてみることにしました。
釣り人が言う稲渋が魚を死に追いやる説
稲渋が魚を死に追いやるという説を見てみると…
- 稲刈り直後に大雨
- 大量の「稲渋」が田んぼから水路、そして河川へ流入
- 稲渋で川は濁り、魚は稲渋によって酸欠(?)となり、大量死する
というもののようです。
待って全然わからない…稲渋ってそもそも何?
名前からして「駆られた稲から出る渋み成分」という意味で呼ばれているんだろうけど、植物の「渋み」が川に入ってきたら酸欠になるって一体…
考えれば考えれるほどよくわからなくなったので、とにかく色々調べてみたのですが…なんとなくその正体が明らか(?)に…
稲渋の正体
結論から言えば、稲渋の主な正体は「ポリフェノール」なんだと思われます。
ポリフェノールと聞くとワインなんかがすぐに思い浮かぶかと思いますが、ポリフェノールは植物の主な渋み成分となっています。

調べていくと「稲ポリフェノール」に関する九州大学農学部の論文を見つかり、読んでみると【稲から約20種類ものポリフェノールの存在を認めた】というお話も…
というわけで恐らくは
- 稲刈りにより稲中のポリフェノールが圧搾される
- 降雨で雨水にポリフェノールが溶解される
- 水路を通じて河川へ流出する
ということには間違いのでは、と…

懸濁物質+ポリフェノールで溶存酸素が低下?
そんなわけで、もう私は“稲渋=ポリフェノール”と勝手に仮定することにしました。笑
しかしそう考えてみると、なんとなくつじつまがあってくるような…
というのも、まずは台風などで「濁り」の原因となる懸濁物質(すごく小さい土とかの粒子)が水中を大量に舞います。
そうなると、当然ながら水中には光が非常に届きにくくなります。
そして植物プランクトンの光合成はあまり行われなくなり、水中の溶存酸素は中々増えなくなります。
#霞ヶ浦 湖面は底の砂が巻き上げられているのか茶色に濁っていました。堤防に打ち寄せる高い波に少し恐怖を感じました。水位が低かったにもかかわらず、堤防を越える波しぶきがありましたが、大きな被害は今のところ確認されていません。 pic.twitter.com/bMI37p0lM9
— 国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 (@mlit_kasumi) September 10, 2019
加えて、そこに大量のポリフェノールが存在するとします。
ポリフェノールはよく「抗酸化作用で身体にいいのよ」なんてうたわれますよね。
抗酸化作用=酸化を防止する=自分が酸素と結びついて酸素を消費する…
つまりポリフェノールなどの抗酸化物質となりえるものが水中に多量にいた場合、溶存酸素も消費されて少なくなってしまうのではないか?っていう…
「水中で抗酸化物質が多量にあると溶存酸素が低下する」という学術的な知見を見たわけでもなし、実際水中でポリフェノールがどう溶存酸素と反応するか全然はっきりわかっているわけではないのですが…
もしかしてそんなことが起きていたら、濁りによって溶存酸素上昇が抑制されることに加えて、溶存酸素がポリフェノールによって消費されたとしたら…
河川中は酸素欠乏状態になるのでは?と…
激濁りによるハクレンの異常行動も?
そしてもう一点気になっているのが、SNSなどに挙げられていた大量死している魚の画像をズームしてみると、そのほとんどがハクレンだったということです。

酸素欠乏症は多くの酸素が必要となる大型魚ほどなりやすいものなのですが、ハクレンが多すぎないか?と…
※逆に小型魚ばかり死んでいて大型魚は生きている場合は、農薬や毒物等の急性毒性物質が流れた疑いが強まります。
そうなると頭をよぎるのは「ハクレンの産卵行動」です。
ハクレンは6~8月頃に、台風で利根川が激濁りすると、産卵行動が誘発されて一斉に産卵し始めるというのは有名な話ですが、それと同じような行動が濁りで誘発されたのでは?と。
※ハクレンの生態について詳しくはこの記事に書いています↓
最終更新日:2023年5月31日 ルアーフィッシングをしている人にはちょっと厄介な存在、ハクレン。 霞ヶ浦水系を中心に生息している魚ですが、現在では結構様々な水域に見られ、関東在住の釣り人からすると、お馴染みの淡水魚かと思います[…]
ハクレンは春頃になると、霞ヶ浦周辺から、利根川を遡上してきて、6~8月に利根川にて産卵行動を終えると、また霞ヶ浦に戻っていくというサイクルを繰り返すので…
霞ヶ浦水系に溜まっていたハクレンたちが一斉に疑似産卵行動?のようなことをして、一か所に集中した
→ ただでさえ酸素が少ない状況なのに大型魚の密度が異常に高くなり、みんな酸素欠乏症に…(涙)
なんていう妄想をしたのですが、どうでしょうか…
一応まとめ
正直ニュースやSNSの情報だけのエアプなので、全て机上の空論ではあるのですが、「稲渋で魚が死ぬ!」という都市伝説について考えてみました。
一応まとめますと…
- 水中に大量の懸濁物質が舞って植物プランクトンの光合成が阻害されて溶存酸素が低下する!(かもしれない)
- 稲渋(ポリフェノールなど)の抗酸化作用により、溶存酸素が消費される!(かもしれない)
- 濁度と水位の上昇でハクレンが疑似産卵行動を起こすことで一か所に集まってしまい、一斉に酸素欠乏症になる!(かもしれない)
という感じ…
あと、もう1つ付け加えれば、多量の懸濁物質が大型魚のエラ表面に付着することで閉塞してしまって…ということも考えらるのかな?と。
あくまで自分の妄想なんですが、「稲渋で魚が死んだ」という話がどうにも腑に落ちなかったのでこんな妄想を描いてしまいました。
皆さんはどう考えますか?
もしも詳しい知見をお持ちの方がいらっしゃったら、是非お教えてください!!m(__)m
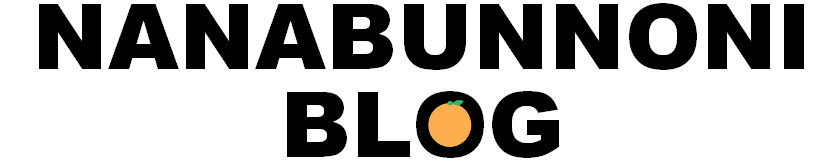
![渋取剤 KBT [ 頑固な稲シブを落とす 洗浄剤 ]18L サンエスエンジニアリング オK【代引不可】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/plusys7022/cabinet/sakai/403371.jpg?_ex=128x128)
