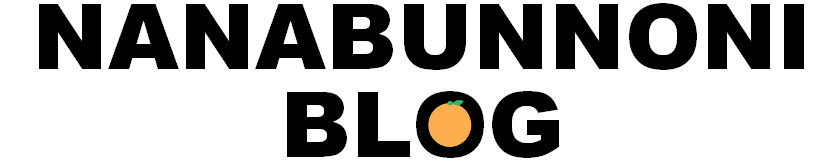振動子ポールの自作方法をまとめておきます。
過去にも多くの釣りブロガーさんがこの手の記事を書いているので今更感ありますが、魚探入門者の方になんかしら参考になれば幸いです🙏
振動子ポールを自作しました
そんなわけで、前回の【カヤック用に魚探買ったよ記事】の続き的な感じで、今回は振動子ポールの自作についてです。
冒頭でも書いているとおり、今更感ある内容ですが、まぁ当ブログ的には新鮮なネタなので、記事にまとめることにしました。
そんなわけで作った振動子ポールがコチラ(結論ファースト)👇

うん、特別なことのない、アルミ素材の角パイプとRAMマウントを使った、よくあるDIYですね。汗
といっても自分は魚探を買った当初、「振動子ってどこにどう取り付ければ?振動子ポールとは?」というレベルだったので、色々とネット情報を探しました…
で、見つけて参考にしたのがイカヒメさんのブログ記事でした👇
あ、コレお友達だからリンク貼ってるとかじゃなくて、普通にめっちゃこの記事を参考に作ったから貼ってますよ。
ちなみにイカヒメさんの記事では、ガーミンのエコーマッププラス93SVに使用している振動子「GT52 Transducer」の取り付けを行ってます。
同じ振動子をお使いの方はイカヒメさんの記事の方が全然イメージつきやすいと思うので、どうぞikahime.netへお飛びください。笑
そもそも振動子って?どこに付ける?
一応魚探を全く使用したことのない方向けに、そもそも振動子ってなんぞや、普通どこに付けるもんなんや?ってあたりも書いておきます。(知識ある方は読み飛ばしてね)
振動子は一言でいえば魚探にケーブル接続するセンサーです。
そのセンサーを、水の中に入れるなりして水温やら水深やらを測るってやつです。(超ザックリ)
振動子の取り付け場所は「絶対にここじゃなきゃダメだよ!」というのは特にないかと思われますが、一般的には…
- エレキのヘッドに直接取り付けるか
- 振動子ポールに取り付けるか
大体はこの2択かと思います。
エレキヘッドに取り付ける場合には、魚探とは別売りの金具が必要になります。


んで、自分の場合は、レンタルボートでエレキ使用時だけでなく、カヤックでも魚探を使用する場合があるため、振動子ポール形式にすることにしたわけです。

振動子ポールを作る材料
前置きが長くなりましたが、ここから振動子ポールを作っていきます。
必要なものは以下のとおりで、大型ホームセンター、ボート用品に強い釣具店、ネットショップなんかで揃えましょう。
- アルミ角パイプ(2mm厚、3センチ×3センチ×長さ1m)
- M4ビス、ナット、ワッシャーセット(ビスの長さは1センチ程度)
- ケーブル保護用スパイラルチューブ(長さ1m)
- RAMマウント組(1.5インチボールのもの)
RAMマウント組については、ボート側にどう固定するかで変わります。
例えば自分の場合だと、カヤックのヘリに取り付けたかったので以下のような組み合わせ👇
- タフクローM 1.5インチボール(RAP-404U)
- アーム標準アーム 1.5インチボール用(RAM-201U) または ショートアーム 1.5インチボール用(RAM-201U-B)
- 菱形マウント1.5インチボール(RAM-238U)
※タフクローはサイズがS、M、Lとあるのでご注意を。エレキのシャフトに噛ませたり、ボートのヘリに噛ませて固定する場合はMで良いかと思います。


タフクローを使わずに、バウデッキに固定する場合には、タフクローの部分を何かしらのRAMマウントベース(1.5インチボール用)に置き換えればOKですね。
振動子ポールを作っていく
材料が揃ったところで、実際に組み上げていきましょう。
やることは単純です。
アルミ角パイプを切って穴を開けて、振動子のケーブルを中通ししたら、あとは先端に振動子を固定、逆側にRAMマウント菱形ベースを固定したら終了…
と、この説明だけだとちょっと雑すぎるので、もう少し補足していきます。
まず、アルミ角パイプ。
ホムセンで売られてるのは大体1m単位かと思います。

なので、こいつはカットする必要あり。
長さはレンタルボートやカヤックで使うなら50cm〜40センチ程度です。
あまりに短いと長さ足らずだったら最悪だなと思い、自分はひとまず50センチで作りました。
カットはホムセン(カインズ)で無料貸し出ししてくれていた、高速切断機で。

1mで買ったアルミ角パイプを50センチ、40センチ、端材という感じで切りました。

他のホムセン(ビバホーム)だと1カット100円でやってくれてるとのことでしたね。
切り出したアルミ角パイプは、切り口を軽くヤスリで整えたのち、振動子とRAMマウントベースを固定する用にビス穴を開けます。



これについては、自分は所有している安い電動ドリルで開けました。
2mm厚のアルミくらいなら金属用ドリルで簡単に穴あけできます。(穴を開けるときは最初小さな穴をあけて、その後、太いドリルで拡張していく)
電動ドリルがない場合には、どこかで借りるか買うか…ですね。
最近はDIYブームによりホムセンでレンタル工具をやってるところも増えたので、レンタルもありかと思います。
ですが、釣り人的にはDIYするシーンって結構あると思うので、電動ドリルくらいは所有してても良いのではないかな〜と感じますね。
ビス穴を開けられたら、あとはM4ビスで固定していくだけですね。
自分が購入したホンデックスの魚探(HE-68WB)には、振動子をボートのトランサムに固定する用の金具が入っていたので、それをそのまま活用して、アルミ角パイプとドッキングさせました。



この辺については、振動子の形状によってまちまちになるかと思うので、上手いこと工夫して取り付けましょうとしか言えませんね…(イカヒメさんの場合はアルミ板を一枚咬ませて取り付けしてましたね)
RAMマウントベース側はこんな感じにビス2本で留めるだけ完了です。

あとは角パイプに中通しした振動子と水温センサーのコードを、スパイラルチューブで上手いこと保護してあげれば完成です。

うん、思ったより簡単だったし、満足な仕上がり!!
振動子ポールの自作まとめ
というわけで振動子ポールの自作方法についてまとめました。
ここで紹介したのは、あくまで自分がDIYした内容であって、振動子の種類やボート側の固定方法によって、アルミ角パイプの加工や必要となるRAMマウントが異なっていくので、そこは各々工夫が必要になるかと思います。
あ、あと最後に補足ですが、何故RAMマウントが広く使用されているか?という話。
その理由は、水圧に耐えられる・強い衝撃を受けたときは曲がって衝撃を逃してくれる・簡単に上げ下ろし出来る、この3つを兼ね備えてるからだと思います。
エレキモーターといえど、船を動かしているときは結構な水圧がかかるので、しっかりと固定できなければすぐに曲がってしまうかと思います。
ですが、釣りしてると結構ゴミやら流木やらがボートにぶつかることってあるんですよね…
振動子がどれくらいの衝撃を受けると壊れるのかはよくわかりませんが、そんなわけで一定以上の衝撃が加わった際には曲がって衝撃を逃してくれるフレキシブルなジョイント部分も必要…で、そうなるとRAMマウントが最適解、という感じなんだなと…(みんななんでこんな高い部品わざわざ使ってるんだ?って思ってましたが、使ってみて実感しました。汗)

そんなわけでコスト的にはまぁそこそこかかってしまいましたが、自分のスタイルに合った振動子ポールが作れたので、満足なDIYでした♪
ではでは。
ミンコタのエレキマウント「ツイストブラケット」をショートバウデッキに装着するため、DIYしてみました。 備忘録としてその方法をまとめておきます。 ミンコタ「ツイストブラケット」とは? レンタルボート向けの装備を少しずつ準備中のみか[…]
唐突に感じる方も多いでしょうが、実は数カ月前に、バス釣り界隈で最近なにかと話題のリチウムイオンバッテリーを注文しておりました。 国産リチウムイオンバッテリーは価格的に中々手が出ませんから、注文をしたのはそう、あのサイト「AliExpr[…]