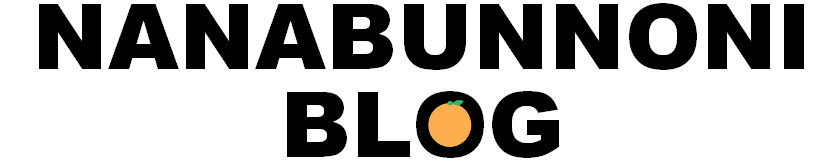先日記事にあげた【TD-Z 103ML】に引き続き、同じ方からTD-Z 103HLもオーバーホールの依頼を受けました。
一般的なベイトリールとは形状が異なる、個人的に興味があったモデルでしたので、喜んで作業させていただきました。
TD-Z 103HL「グリッピングレフト」とは?
さて、タイトルのとおり今回はTD-Z 103HLのオーバーホール。
以前記事にあげたTD-Z 103MLとは何が異なるのか?
その形状を見たら一目瞭然ですよね。

最近バス釣りを始めた人は「ナンジャコレ…」と感じたりするのかな?
一言で表せば【撃ちもの専用ベイトリール】…ですね。
長年バス釣りをやっている一部の方々は、SNS等で「これ代わりが効かないからいまだに使っている」とか「現代技術でグリッピングレフト復活させてほしい」とかいう意見を目にしたりします。
とはいえ、自分からすると、このリールがリリースされた頃はおかっぱり小中学生…
正直このモデルに興味を持つようになったのは、リールいじりを頻繁し出したここ数年の話ですね、これって内部構造どんな風になってるんだろうと…

右ハンドルユーザーということもあってインプレ的なものは自分じゃできません、なので気になる方はGoogle先生に聞いてみてください。苦笑
ちなみに状態を選ばなければ、ベリーネットとかでも普通に在庫はあったりしますね。
早速分解していくよ
前置きはこれくらいにして、早速分解していきましょう。
今回の103HL、確かに前回預かった103ML同様外装は非常にきれいです。(単純に使っていなかったわけではなく、使ってたけど大切にされてきた系の個体)
まずハンドルやらスタードラグやらを外していきまして…


サイドカップとスプールも外します。

んでもってビスを緩めていけば、はいご開帳。

開ける前からレベルワインド周りでなんとなくわかっていましたが、グリスの固着・劣化などは酷い…が!!そんなものは当たり前。(何年前のリールだっつー話。)
いやいやそれどころかしっかりグリスアップされていたおかげもあり(?)、ギアやクラッチ関連パーツの痛みとかは全然ありません。

これはオーバーホールやれば相当良くなる予感しかありませんね。(こういうリールが一番オーバーホールやるの気楽で楽しいんだよなぁ…)


どんな内部構造なのかなとワクワクしながら開けましたが、一般的なベイトリールと比較すると、ドライブギアがダイレクトにレベルワインダーを動かすプラギアに噛んでいる部分や、クラッチの構造が異なるくらいで、あとは特別変わった点はない感じですね。(想像してたよりも全然シンプルな構造)
初見でも適当に記録写真を撮りながらやれば、普通にバラして組み上げできました✌️

組み上げていくよ
さて仕上げ。
グリスやオイルはいつものボアードさんのヤツですね。

依頼者さんから特に注文はなかったので、自分の中でベーシックな組み合わせ、メイングリスはデルタとオメガ、メインオイルはキメラとライトデューティで仕上げました。
バラしながら都度各部の清掃、ベアリングの洗浄とかを済ませていくので、組み上げの時間はほんとにあっという間です…
はい、完成だよ!!

手前味噌ですが、今回はかなーり上手くメンテナンスできたなと感じます。
まぁ流石にいくつかベアリングがちょっと傷んでるものもありましたが、普通に使う分には十分な状態でした。
ハンドル回転時のノイズ感はほとんどなく、依頼者さんにも満足していただけました🙌
TD-Z103HLオーバーホールまとめ
というわけで、サクッとTD-Z103HLのオーバーホールについて書いてみました。
グリッピングレフトを現代技術で復刻されたとしたら、ほんとに結構な話題になるんじゃないかなぁと思うし、需要もそれなりにあるんじゃないかなと…(ベイトフィネス仕様のグリッピングレフトとか関東レンタルボートフィールドでウケそうだけど…)
最近のダイワさんは王者◯マノさんよりもだいぶ攻めの姿勢を見せている印象を感じるし、ワンチャンなくはないのでは?…とか勝手に思ったりして。笑

そんなこんなで、今回はこれでおしまいです。
あ、TD-Z103HL分解の参考資料として、ネットで見つけた展開図を一応貼っておきます。


ではでは🙏
お仕事でお世話になってる方から、TD-Zのオーバーホールを承りました。 備忘録として残しておきますが、結論から言うと中々調節が合わず、だいぶ苦戦を強いられました。汗 2000年初頭の名機「TD-Z」 発売時期を間違えていたらすみま[…]