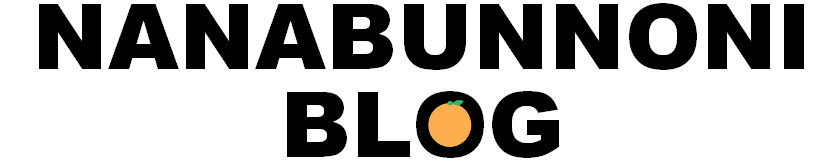リールメンテナンスやカスタムを自分で行う際、当然ながらリールを分解するという作業が発生するわけですが、慣れていない人からすると、かなり億劫だし怖い作業ですよね…
ということで今回はリールを分解する際のコツ的なものをまとめたいと思います。
リールを分解するときのコツ
こんにちは、ここ数年ですっかりリールバラバラにも慣れっこになったみかんです。
もちろん「チューニング」という面ではパーツクリーニングからグリス塗布・オイル注入など沼すぎて、専門の方からすると全然低レベルですが、特にベイトリールに関しては分解・組み上げは基本もう何も見ずにやっています。
しかしこういう作業ってリールいじりを全くしない人からはやっぱり「え?よく自分で出来るね…」なんて言われたりするんですよね(^_^;)
リールの分解・組み上げについては慣れてしまえば全然大した作業ではないのですが、そういう声を聞くと、やったことない人(または滅多にやらない人)からするとハードルの高いものなんだなぁ…と。
そんなわけで今回はリールの分解・組み立てを失敗しないためのコツというか、ポイント的なものについて3つほどまとめました。
1.キレイな机の上で作業する
まずはとにもかくにも第一に「キレイな机の上で作業をする」ということです。

リール部品の中には2、3mmの細かなパーツも含まれているので、慎重に作業していてもやはりパーツを一瞬で見失うこともあります。(Eリングとか小さなワッシャーとかEリングとか。汗)
そんなときに机の上がごちゃついていると、どうにも部品が見つからない…なんてことも。
あと机の下も何も置かずキレイにしておくのが理想です。
机の上からポロリした際に、何かしら物が置いてあると、「そこに紛れたかも?」と捜索の手間が増えることになるからです。
2.分解したパーツを分類して保管しておく
さらに「分解したパーツは分類して保管しておく」というのもポイントです。
写真のトレーは100均で買ってきたトレーなのですが、結構便利です。
例えばハンドル周り、スタードラグ周り、ギア周り、クラッチ周り…という感じに分類して置いておくだけで、取り外したパーツが散らかりませんし、組み上げるときもスムーズです。
さらにワッシャーの向き(裏表)や順番なども忘れないようにしたい場合には、こんな感じでテープで止めちゃうというのも手かと。
慣れてくればここまでやる必要はありませんが、初めのうちはこれくらいやっても良いかもしれませんね。
3.分解中はとにかく写真を撮りまくる
最後のポイントは「もうとにかく分解工程の写真を撮りまくって記録を付けておくこと」です。
リールの構造は言うほど複雑なわけではありませんが、それでもいざ組み上げるときになると「あれ…このパーツの向き、どっちだっけ…汗」となることも。
例えばクラッチヨークなんかはリールによっては反対向きでそのまま付けられちゃうし(そして組み上がったあとにクラッチ切れなくてショック受けるやつ)、先述したワッシャーや座金類の順番なども意外と覚えてられなかったり…
しかし撮影しておいた写真を見返せば元の状態は一目瞭然なので組み上げ時に困らなくて済むのです。
セルフオーバーホールのメリット
セルフオーバーホールは分解したはいいが上手く組み上がらない・作業中にリールを傷つけてしまったなどのリスクも伴いますが、メリットも多くあると感じます。
- お金がかからない
- 預け期間が発生しない
- 自分好みにチューンできる
自分が特に感じるメリットはこれら3つでしょうか。
お金の面については最初は工具類やグリス・オイルなどを揃えるのに初期投資が必要となりますが、揃えてしまえばもうお金をかけることなく自分でオーバーホールが出来てしまうわけですから、長い目で見るとメリットかと。
これまで「いやもちろんグリス切れとかオイル切れはアウトだけど、どのオイルもグリスもちゃんと使っていればそんな変わらないでしょう…」という考えだったみかんさん。 しかしついに手を出した高級オイル&グリス、その理由は?そしてその効果は? […]
あとは何より「預け期間が発生しない」というのはメリットだと感じます。
シマノやダイワにオーバーホールを出したらその期間、そのリールを使えなくなるわけですが、自分でやるんなら数時間でクリーニングから組み上げまで完了できてしまいます。
オフシーズンの冬にオーバーホールを出す方も多いかと思いますが、冬も構わず毎週釣りに行くジャンキーにはセルフオーバーホールがおすすめですね。笑
まとめ
リールを分解・組み上げに失敗しないためのポイント的なものをまとめてみました。
あとはどうしても組み上がらなくなったら【リール名 分解 オーバーホール】とかでググッてみてください、多分誰かしら釣りブロガーが妙に詳しい解説記事を書いているはずです。笑
自分でやるリスクも勿論ありますが、リールの構造やチューニング・カスタムに対する知識も深まるので、こういった作業を楽しめる方は是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか♬